 あさみ
あさみこんにちは!あさみです
海外への「親子留学」を目標に、毎日2歳の娘と英語を勉強中!
自分の経験をもとに「子どもの英語」に役立つコンテンツやノウハウを書いています!
私には、自身のお子さんが2歳頃から英語学習を始めたという先輩ママが何人かいます。
そして、その全員から言われているのが、
英語を習い始めて半年~1年が経つと、絶対に英語イヤイヤ期が来るよ
という話。
幸いにも、我が家の娘にはまだ「英語イヤイヤ期」は訪れていませんが、絶対に来るのであれば、対処方法を事前に知っておきたい!
ということで、
・なぜ子供には英語イヤイヤ期が訪れるのか?
・またその対処方法は?
について調べてみました。
今まさに、英語イヤイヤ期に苦労しているママ&パパの参考にもなれば嬉しいです。
2歳児が英語を嫌がる理由はこれ!


2歳頃から英語を始めた子供が、半年~1年も経つと英語を嫌がってしまうのはなぜなのか?
それは主に以下の4つの理由があるんだそう。
子供が2歳~3歳頃というと、母国語(つまり日本語)でのコミュニケーションが急激に上手になる頃です。
そして、できることを喜んで(積極的に)やるのが子供です。
つまり、英語より日本語のものを楽しんだり、英語で話しかけても英語ではなく日本語で話したくなるのは当たり前のことなんですね。
私たち大人だって、もしフランス語と日本語の両方が話せるハーフの友達がいたとしたら、その友達とフランス語で話したいと思いますか?



両方話せるなら、私がよく知ってる日本語の方で話してよ~。
何でわざわざフランス語で話すの~。
と思いますよね^^;
英語イヤイヤ期のお子さんというのは、これとまさに同じ状況だということです。
小さい頃はまだあまりわかっていなかったから、英語も日本語と同じようにそのまま受け入れていたけど、2歳~3歳にもなれば



ママは日本語も話せるんでしょ!
だったらわざわざ英語で話す必要はないよね
と気づいてしまい、だからこそ英語を拒否するようになってしまうんだそう。
にも関わらず、ここでさらに英語の勉強を強要するような事をしてしまうと、イヤイヤは益々助長されてしまいます。
英語イヤイヤ期はこう乗り切る!原因別対処方法まとめ
もし自分の子供に「英語イヤイヤ期」が訪れてしまったら、どんなふうに対処すればいいんでしょうか?
原因別に解説していきたいと思います。
【子供に英語イヤイヤ期が訪れてしまう原因】
①英語より日本語の方が分かるから
②動画や絵本を英語で見聞きする理由がないから
③親は日本語で話しても通じると気づいたから
④勉強を強要されるから
①英語より日本語の方が分かるから→英語のインプットを増やし、日本語との理解の差を縮める


まずお子さんを観察してみてください。
そしてもし、イヤイヤの原因が「英語が分からない」ということにありそうだなと感じたら、英語も日本語と同じくらい「分かる」ようにするために、英語のインプットを増やしてあげるのがいいですよ。
私もそうですが、早期英語学習に取り組んでいるほとんどの人は、自分ではちゃんとインプットができていると思っているんだそう。
でも実際は、
・英語のかけ流しの時間が少ない
・歌の動画やかけ流ししかしていない
など、英語のインプットが十分でないことがしばしば。
そうすると、日本語と英語の理解度に差が生まれてしまい、「英語は嫌、日本語がいい」となってしまうんですね。
あなたのお子さんは、日本語のインプット時間に対して、英語のインプット時間はどのくらい確保できていますか?
もし日本語に対して英語の時間が少なければ、そのままでは英語と日本語の理解の差は縮まりません。
・英語のかけ流しの質と量(時間)を増やす
・英語動画の内容を見直す
・英語絵本読み聞かせを増やす
など、もっと英語のインプット時間を増やすと、英語への興味がまた戻るかもしれません。
②動画や絵本を英語で見聞きする理由がない→英語でしか味わえない「好き」を与える



インプット時間を増やすのは分かったけれど、そもそも英語で動画を見ることや、英語の歌を流される事を嫌がる・・・
これは、「英語イヤイヤ期」のお子さんにはよくある事なんだそう。
そしてそんな時は、今あなたがお子さんに与えているモノを見直す必要があります。
例えば、あなたがYoutubeで英語の動画を見せていた場合、その動画は、お子さんの年齢にあったものですか?お子さんが好きなジャンルの内容ですか?
他にも、あなたが英語の歌の聞き流しをしていた場合、お子さんは歌が本当に好きですか?実はダンスの方が好きだったりしませんか?
英語離れをしている時期は、今やっていることに拘ったり、無理やり子供に英語を話させようとすると益々子供は英語を嫌がります。
それよりも、
英語でしか味わえない好きな物を見つけてあげて、子供が自ら「英語が楽しい、見たい、やりたい」と思うようにしてあげることが大事です。
こういった時は、巷で有名な高額英語教材や、効果があると言われる方法も、一旦は無視です^^;笑
とにかく、お子さんが好きなもの、興味のあるものです。


もし恐竜が好きなお子さんなら、恐竜がたくさん出てくるアニメを見つけてあげてください。
そうすれば、



本当は日本語で見たいけど、英語でしかやっていないなら英語で見る
となるはずです。
そうやって、子供の「好き」から少しずつ、日常にまた英語を広げていけば、子供の英語への関心は必ず戻ります。
そして子供の英語への関心が戻れば、徐々に先ほど紹介したような方法で、英語のインプット時間を増やしてください。
「英語イヤイヤ期」のお子さんに一番大事な事は、「英語から離れないこと」「英語を嫌いにならないこと」です。
③親は日本語が通じると気づいてしまった→英語でしか話せない相手を与える
次は、家で英語を話さなくなってしまったという子供に対しての対処法です。
3歳にもなれば、親は日本語でも通じるとバレているので甘えが出たり、親とは違う言語を話す恥ずかしさもあって、英語で話しかけても日本語で返答する子供が増えてくるんだそう。
そういう時は、、、
英語でしか話せない相手をお子さんに与えてあげてください。
家の中にいて、親子だけでの会話だと、シチュエーションも内容も限られますよね。



そもそも親がバイリンガルレベルじゃないと、つっこんだ内容の英語のレパートリーも少ないし・・・
すると、親となら英語で話せる子が、いざ本当に英語圏の人と話そうとすると、思ったように言葉が出てこないというのは普通にあることらしいです。
なので英語でしか話せない相手を与えるというのは、「英語イヤイヤ期」を乗り越えるためだけじゃなくても、大事なことなんだそう。
ちなみにおすすめは、
オンライン英会話教室の無料体験を使い倒すです


| 教室名 | ネイティブキャンプ | Kimini英会話 | リップルキッズパーク | クラウティ | QQイングリッシュ | ハッチリンクジュニア | Musio English | GLOBAL CROWN |
| 無料体験 | 7日間 | 10日間 | 2回 | 8日間 | 2回 | 2回 | 14回 | 2回 |
| おすすめポイント | 回数無制限!予約いらず! | 教育のプロ・学研が提供 | ABCから始められる「子ども専門サービス」 | アカウントを6人でシェアできる | 初月無料キャンペーンあり! | アカウントを家族でシェアできる | AIロボットレンタル×オンライン英会話 | 日英バイリンガル講師で日本語フォローOK! |



無料体験の回数無制限の「ネイティブキャンプ」は
特におすすめ!
コロナ禍を経て、オンライン英会話サービスの数って劇的に増えましたよね。
そしてどのサービスも絶対無料体験は実施しています。



次の冬休み、時間がたっぷりある時に、試してみるのはいいかも!
まずは無料体験を渡り歩くことで子供の英語への興味を復活させ、もしそのまま続けたい言われたら、入会を検討するのもいいですよね。
④子供に勉強を強要してしまっている→英語を学ばせる意識を捨てる
子どもが英語を嫌がる理由でも触れましたが、、、
「子供に英語を勉強させよう」という意識が強すぎると子供は英語を嫌がります。
親の思いが、お子さんのプレッシャーになってしまっているんですね。
お子さんにプレッシャーを与えないよう、
英語は学ばせるものではなく、子どもが主体的に学ぶもの
と肝に命じておくのが大事だそうです。
「英語は子どもが主体的に学ぶもの」と子供自身が思えれば、「早く勉強しなさい」など声をかけなくて済むので、親自身のストレスもなくなりそうで、一石二鳥ですね^^
まとめ
子供に「英語イヤイヤ期」が訪れたら、英語でしか楽しめない「好き」を見つけてあげることで、もう一度英語への興味を復活させる
英語イヤイヤ期は絶対くるよ・・・
と話していた先輩ママ達ですが、実は、、、
「英語イヤイヤ期」は絶対乗り越えられる
ということも全員から言われました。
なので、諦めて英語から離れてしまうのではなく、子供の「好き」を第一優先に、根気よく英語を続けることが大事なようです。
みんな一度は通る道!
一度乗り越えてしまえば、あとは楽になる!
と思って頑張って乗り切りましょう!

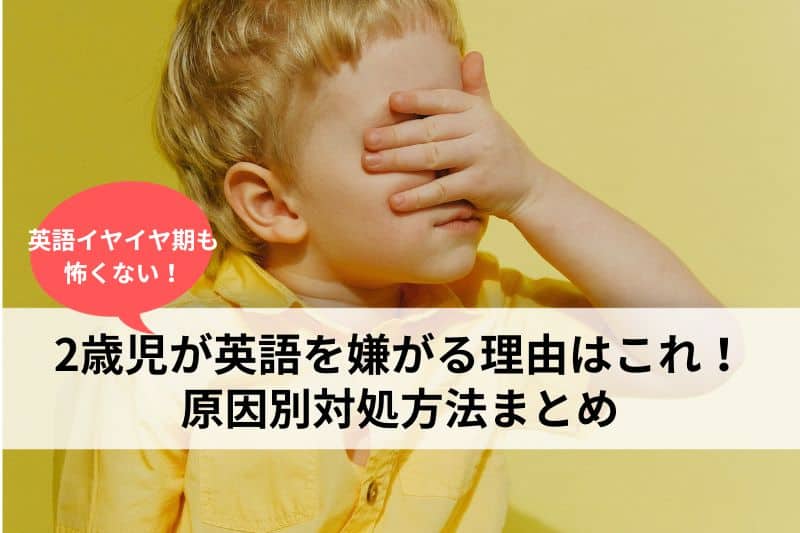
お気軽にコメントをどうぞ