 あさみ
あさみこんにちは!あさみです
海外への「親子留学」を目標に、毎日2歳の娘と英語を勉強中!
自分の経験をもとに「子どもの英語」に役立つコンテンツやノウハウを書いています!
我が家の娘(現在2歳)は、インターナショナルプリスクールに通っています。
最近では、プリスクールの数が急激に増えたので、幼稚園や保育園ではなく、プリスクールに通わせたいと思われる方も多いですよね。
でも自分達が経験していないだけに、プリスクールってまだまだ未知の場所じゃないですか?
・幼稚園や保育園とは何が違う?
・学費はやっぱり高い?
・親の英語力はいるの?
・英語はほんとに身につくの?
・日本語の発達に遅れはない?
などなど。



まさに1年前の私がそうでした
そこで、1年前の自分に向けて、インターナショナルプリスクールのあれこれを解説していこうと思います。
そもそもプリスクールってどんな所?


最近では、プリスクールの数も増えてきたとはいえ、プリスクールってそもそもどんな所?と思っている人は、多いですよね。
まずは、一般的な幼稚園や保育園とプリスクールの主な違いをまとめてみました。
| プリスクール | 幼稚園 | 保育園 | |
| 認可or認可外 | ほぼ認可外 | 認可も認可外もある | 認可も認可外もある |
| 言語 | 英語(日本人保育士がサポートすることが多い) | 日本語 | 日本語 |
| 保育時間 | 園によってバラバラ | 4時間(標準) | 1日最大11時間 |
| 通える年齢 | 園によってバラバラ (0歳から通える園も多い) | 満3歳から | 0歳から |
| 園児の数 | 少人数保育の園が多い | 1学級35人以下 | 規定なし |
| 学費 | 年間100~200万 | 認可:年間約30万 私立:年間約50万 | 認可:年間約30万 私立:年間約50万 |
| 免許 | ・保育士は保育士資格が必須 ・英語講師には資格や免許の義務はなし | 幼稚園教諭免許必須 | 保育士資格必須 |
プリスクールと幼稚園・保育園の大きな違いは、プリスクールでは一日のカリキュラムをほぼ英語で行うということです。
そのため、生きた英語に自然と触れることができるというメリットがあります。
また、プリスクールはほぼ認可外の園しかないというのも大きな違いで、認可の幼稚園や保育園と比較すると、学費は3倍程度かかってしまいます。
ちなみに私の娘が通っているプリスクールは
・少人数制の縦割り保育を実施
・0歳からの預かりOK
・1日最大9時間までの保育
・英語講師3名、日本語保育士2名の保育体制
・学費は約80,000円/月(給食費、おやつ費込み)
というような園に通っています。
次にプリスクールに関する疑問について紹介していこうと思います。
※以下の情報は、娘が通っているプリスクールの情報を元に紹介しています。他の園も必ずしも同じような状況ということではありません。
オムツ外れは必須?


これは園によってバラバラだと思いますが、その園が何歳からの子供を受け入れているかによって変わってくると思います。
0歳児からの受け入れが可能な園ならもちろんオムツが外れている必要はないですが、満3歳からしか入園できない園なら、オムツ外れが必須になっている園も多いかもしれません。
ちなみに娘が通う園は、入園時点でオムツが外れている必要はなく、今まさに園と協力してトイトレをしています。
プリスクールには必ず日本人の保育士がいるので、トイトレや食事のしつけなど、保育園や幼稚園でやってもらえるようなことは、プリスクールでも問題なくやってもらえます。
給食orお弁当?


プリスクールはほとんどが認可外保育施設なのですが、認可外保育施設というのは園の中に調理室を設ける義務はありません。
そのため、お弁当を持参しなければいけない園は多いと思います。
娘が通っている園では、園で契約したケータリングのお弁当を購入するか、お弁当を持参するかのどちらかなんですが、ケータリングのお弁当が魚食を中心としたメニューになっているので、ほぼ毎日購入しています。



家では魚なんてほとんど拒否するくせに、
お友達一緒だと食べるんですよね~
スクールには感謝でいっぱいです。
どんなカリキュラムがある?
娘が通う園では、朝は英語のリズム体操から始まり、外遊びや英語絵本の読み聞かせ、キッズダンス、アルファベットの発音練習などがあります。
またアートやクラフトに力を入れている園なので、フラワーアレンジメントやバイオリンといった授業があったり、母の日や父の日といった時には、すごく凝ったモノを作ってプレゼントしてくれます。


また、昼食時に「いただきます」の代わりに「その月の英語の歌」を歌っているようで、毎月新しい歌を覚えて帰ってきます。
英語に触れられるというのはもちろん、家ではなかなかできない経験をしてきてくれるのは、親としてはかなり嬉しいです。
1日のスケジュールは?
これは、娘が通うプレスクールの1日のスケジュールです。
| 8:00 | 開園 | |
| 10:00 | 朝の歌・体操 | 朝の挨拶の代わりに英語の歌をうたい、体操も英語で行う |
| 10:30 | 外遊び | 校庭がないため、毎日近くの公園に行き、約1時間体を動かす |
| 11:30 | 昼食 | お弁当の持参か給食の購入が選べる |
| 12:30 | お昼寝 | 0歳~3歳までの園児はお昼寝をし、4歳~6歳までの園児は知育活動をする |
| 15:00 | おやつ | 3食の食事では摂りきれないものを補うよう、野菜・果物・魚を中心とした手作りのおやつをだしてもらえる |
| 15:40 | 知育活動 | 英会話やリトミックなどの授業、学習室でのお勉強、クラフト・ブロック遊びなど脳の発達に重点をおいた活動を行う |
| 17:00 | 自由時間 | 各自のお迎えの時間まで、好きな事をして遊ぶ |
| 18:30 | 夕食 | 最大22時までの預かりが可能なため、夕食を希望することもできる |
年間行事は?


遠足や学習発表会、運動会といった一般的な保育園や幼稚園で行われる行事ももちろんありますが、イースターやハロウィーン、クリスマスといった英語圏にちなだお祭りも盛大にお祝いします。
他にも、春はひな祭りやお花見、夏は七夕祭りやスイカ割り、冬はお正月や豆まきと日本の文化にそったイベントもたくさん企画してくださるので、娘も楽しく園に通っています。
どんな子供が通っている?


娘の通う園では、日本人の生徒が多いですが、外国人ファミリーが多く住んでいる地域だということもあり、中華圏や英語圏のお子さんも通われています。
小さな頃から、色々なルーツをもったお友達ができるのは、プリスクールに通わせるメリットの一つだなと思っています。
また生徒のママ&パパは、やっぱり英語教育への関心が高い方が多いです。
親も英語が喋れないとダメ?


娘の通う園では、日本人のスタッフも多いですし、園からのお便りも日本語で作られたものがもらえます。



なので、私の英語力は全く問われません^^;
でもやっぱり外国人の先生たちと直接お話はしたいんですよね。
特に娘の園では親子遠足が多いので、そういった時に先生とコミュニケーションが取れないのはやっぱり残念で・・・
ということで、今私は娘と一緒にもう一度英語の勉強を始めています。
こちらの記事では、私が英語の勉強用に活用しているアプリを紹介していますので、気になる方は、合わせてチェックしてみてください。
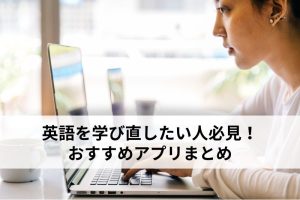
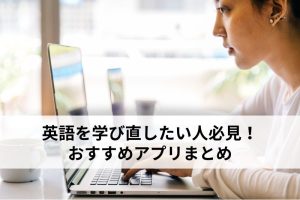
プリスクールに入ろうと考えた理由は?
私の娘は、2歳になる年の4月からプリスクールに通っています。
私が仕事復帰するタイミングだったので、プリスクールじゃなくても、保育園には行ってもらわないといけなかったんですが、なぜあえてプリスクールに通わせようと思ったのか。
それは、、、
・本物の英語に触れて欲しかった
・自宅で英語学習の時間を確保する自信がなかった
というのが大きな理由です。
元々、幼児に対する英語教育には関心があったので、そのことについて色々勉強はしていたんですが、
その結果、、、
・ネイティブの英語を聞かせること
・子供が楽しんでいること
・敢えて勉強するんじゃなく、英語が日常であること
・毎日コツコツ継続すること
がすごく大事だと知りました。
ただ園探しをしていた1年前の私は、ネイティブにはほど遠い英語力でしたし、仕事が始まってしまうと、家で英語の時間を確保する(しかも毎日)というのは無理だと思ったんです^^;



おうち英語で頑張られてるママ&パパは本当に尊敬します
なので、どうせ保育園に入れるのなら、同じ時間で英語にも触れられるプレスクールに行ってもらおうと考えました。
【実体験】2歳からプリスクールに通わせてよかった理由3選!
私は2歳の娘に対し、保育園ではなくプリスクールに通ってもらうことを選択したわけですが、約半年が経った今、プリスクールに通う事を選択して本当によかったなと思っています。
その理由は、以下の3つのことにあります。
・英語に苦手意識がない
・表現力が豊かになった
・多様性を自然に身につけられる
英語に苦手意識がない
プリスクールに約半年通った現在の娘の英語力ですが、英語で指示されること(sit downやclean up、pass meなど)は完全に理解して、行動に移すことができます。
また挨拶(Good mornign、Hello、See youなど)や色、果物など簡単な単語なら、英語が出てくるようになりました。
他にも、10までなら英語で数が数えられるようになりました。
【娘の現在の英語力】
・英語を聞き取る力はついた
・英語を話す力はまだまだこれから
さらにこの半年で、英語のことが大好きになってくれたと思っています。


例えば夜の読み聞かせの時、英語と日本語、どちらの本がいいか必ず確認するようにしているんですが、最近では英語の本を選ぶことの方が多くなってきました。
今のところ、娘は英語に対して苦手意識がないようなので、これからも楽しみながら英語を学び続けてくれるんじゃないかと思っています。
学び続けてさえいれば、英語を話す力もいつか爆発的に伸びる時が来ると思うので、今からそれが楽しみです^^
表現力が豊かになった
この半年、プリスクールで身につけたのは英語力だけではもちろんありません。
娘の場合は、、、
表現力がものすごく豊かになったように思います。
娘は元々すごくシャイです。


例えば、初めての場所だったり人に会うときは、お気に入りの毛布を握りしめていないと怖い・・・
というぐらいシャイな子だったんです。
それがプリスクールに通いだして半年、今では「安心毛布」は手放せるようになりましたし、新しい友達に出会っても、自分から声をかけるようになったのには、驚かされました。


外国人の先生って、感情表現が豊かなんですよね。
体を使って思い切り遊んでくれたり、ハグや言葉ではっきりと愛情表現を示してくれます。


娘もそれに影響を受けたのかもしれません^^
多様性を自然に身につけられる環境がある
娘の通う園は、ほとんどが日本人の生徒ですが、ハーフの友達も外国籍の友達もいます。
また縦割り保育を実施している園なので、年齢がバラバラの生徒が毎日一緒の時間を過ごします。


さらには、イースターやハロウィン、クリスマスといった外国のイベントも楽しみます。
このように、
世の中には様々な人がいて、様々な文化や宗教があるということを、実体験を通して感じてくれる環境が整っているのは、プリスクールに通うメリット
だなと思っています。
費用面での覚悟は必要?プリスクールのデメリットは?
プリスクールに通っていると、いいことしかないのかというと、もちろんそうではありません。
一般的に言われるプリスクールのデメリットには、次のようなものがあります。
・学費が高い
・設備が整っていない
・日本語が疎かになる
学費が高い


一般的なプリスクールは、授業料が1日5,000〜10,000円くらいかかるので、毎月の授業料は例えば週2回通うなら4〜6万円程度で、週5日通えば10万円ほどになります。
一般的な保育園と比較すると3倍ぐらいの学費ですね^^;
ちなみに娘の園の場合は、授業料にプラスして給食費や施設費、保険料など全て込みで月80,000円程度です。



高い・・・
高いことに間違いはないんですが、娘は週6日、朝8時半~17時まで預かってもらっていて、英語以外にも日本語教室、体操、ダンス、バイオリン、フラワーアレンジメント、工作など様々なカリキュラムを経験させてもらっています。


到底家では同じだけの経験はさせてあげられないし、もし1つ1つを別の教室でと考えたら、もっとお金がかかるんじゃないのかなぁと。
なので、私はこの金額にも納得して、娘をプリスクールに通わせています。
また最近は、幼児教育無償化の対象となっている園も多いです。
そうすると、満3歳以上からは負担もかなり軽減されるんですよ。
【幼児教育無償化制度】
認可外保育施設の場合、3歳から5歳までの子供たちは、月額3.7万円まで補助を受けられる
設備が整っていない


幼稚園と保育園との違いでも説明したように、認可外保育施設であるプリスクールには、調理室や園庭を設ける義務がありません。
なので、設備に不満をもつ方は多いかもしれません。
実際、娘が通う園も校庭はなく、ビルのワンフロアを活用した園です。
正直にお話すると、初めて見学にいった時は「せまっ!」と思いました^^;
校庭がないのも、外遊びの時間はちゃんと確保してもらえるのかな?という不安もありました。


ただ実際に通ってみると、毎日近くの公園に1時間程遊びに出かけているようですし、運動会も地域の小学校と連携し体育館を借りて行うなど、校庭がないことのデメリットはほぼ感じていません。
園自体の狭さについても、大人の私がそう感じただけで、娘たちが特に不便を感じている様子もありません。
日本語が疎かになる
私が娘をプリスクールに通わせると親や友達に話した時、



日本語の発達が遅れない?
と全員から言われました^^;
いわゆるセミリンガル問題ですね。
【セミリンガルとは】
複数の言語を話せるけれども、そのどれもが年齢相応に発達していない状態や、そういう人
確かに、私もその心配がなかったわけではありません。
なので、プリスクールへの入園を決める前にセミリンガル問題について勉強をしました。
結果、、、
一日の中で、英語のシャワーを浴びさせる時間と日本語のシャワーを浴びさせる時間をバランスよくとれば、どちらかの言語の発達が遅れることはない。
というのが分かりました。
2023年9月2日にNHKの番組「すくすく子育て」で幼児期の英語学習に関する特集がありましたが、その番組内でも専門家の先生が同じことを話されていましたよ。
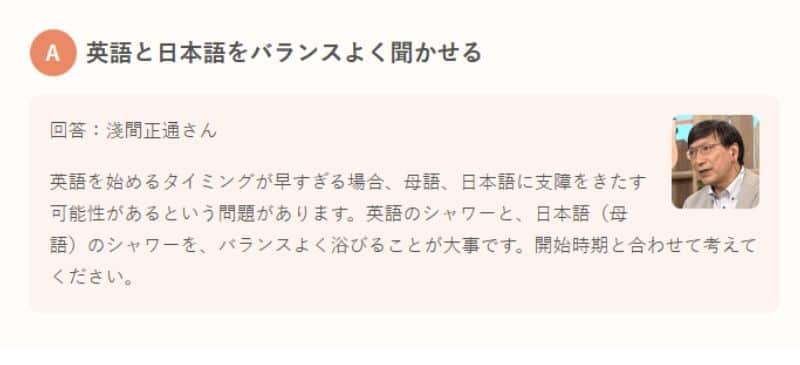
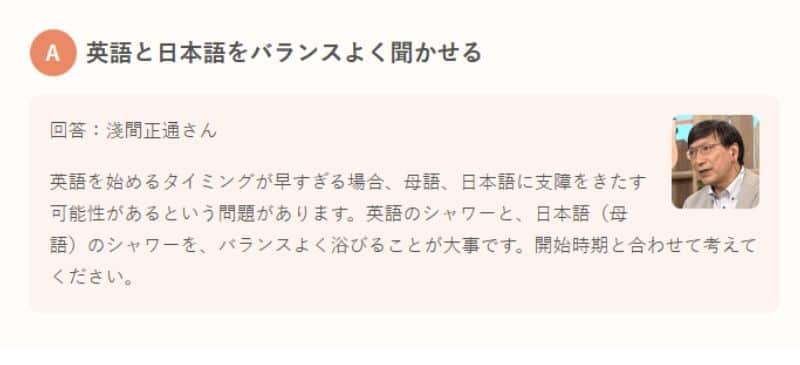
私の場合ですが、娘は日中プリスクールで英語のシャワーを浴びまくっていると思うので、家に帰ってまで英語漬けにするのではなく、晩御飯やお風呂の時間には日本語で娘の話をしっかり聞くようにしています。
また私が選んだプリスクールには、日本語を学ぶ時間もしっかり確保されているんですよね。
セミリンガル問題を心配される方は、そういったカリキュラムが整ている園を選ぶといいかもしれません。
失敗なし!プリスクールの選び方


ちょうど1年前、娘のスクール選びをしていた時、トータル5校ぐらいのプリスクールに見学に行き、通うプリスクールを決めたのですが、自分の選択に間違いはなかったと自負しています。
私がプリスクールを選ぶ時に重視した点は、
・園長との相性
・歴史
・家からの通いやすさ
・学費
・どんなカリキュラムが用意されているか
園長との相性


プリスクールの見学に行くと、園の運営方針やどんなカリキュラムがあるか、実際の授業見学など、園長先生が対応してくださることが多かったです。
本当に様々な園長がいて、中には絶対保育に関わっていないですよね?と思うような園長先生もいました。
その先生は、園内でピンヒールを履いていたんですよね^^;



その靴では、子供は追いかけられないよー!!
今通っているプリスクールの園長は、通っている生徒全員を自分の孫みたいに可愛がられているような先生です。
あーきっとこの先生が運営している園なら、アットホームな雰囲気の園なんだろうなぁと思っていたら、実際に通ってみても本当にその通りで、娘も毎日安心しながら園に通っています。
登園初日から今まで1回も泣いたことがないんですよね^^;
きっと娘と園の相性がいいんだと思います
歴史
幼児への英語教育がブームだからか、近年プリスクールの数も一気に増えましたよね。
私が住んでいる地域でも、通える距離の範囲に5校もあったぐらいです。
歴史が浅いスクールが全てそうだとは思いませんが、最近できたプリスクールの中には、このブームに乗っかっておこうと作られた園も多いんじゃないかと私は思っています。
そういった園はノウハウがないので、先生の質が悪かったり、教育の質が悪かったりしますよね。
その点、今娘が通っているプリスクールは設立から30年の歴史があって、教育に対して確固たるノウハウのある園でした。
例えば、英語学習以外にも日本語学習に力を入れているというのも、長年の経験からだと園長は話されていました。
こういったプリスクールなら、子供を安心して通わせることができますよね。
家からの通いやすさ
毎日の送り迎えや、緊急の時に迎えに行くことを考えた時に、自宅から通いやすいというのは、かなり大事なポイントだと思っています。
ちなみに、今娘が通っているプリスクールは、自転車で10分で通うことができます。


今の園と最後の最後まで迷った別のプリスクールがあるのですが、それはバス通園が必要な園だったんですね。
月々のバス代も追加になってきますし、何かあった時にすぐに迎えにいけないのはデメリットかなと思い、今の園に決めました。
学費
学費はそれぞれのプリスクールで全く異なってくるため、支払わなければいけない授業料に対し、納得できるだけのカリキュラムが用意されているかはチェックした方がいいと思います。
私が見学に行った5校も、バラバラの金額設定だったんですが、中には、この授業料は、家賃をまかなうための金額設定ですよね?と思うぐらい、授業料とカリキュラムの内容がマッチしていない学校もありましたよ^^;
どんなカリキュラムが用意されているか
一概にプリスクールと言っても、園によって特徴はバラバラです。


例えばアートに力を入れているや、運動に力を入れている等。
そして、園が用意しているカリキュラムを見れば、その園がどんな園かということも分かると思います。
私が見学に行った5校の中には、卒園までに英検3級に合格できる!ということを売りにしていて、お勉強系のカリキュラムが充実しているプリスクールもありました。


私の場合は、セミリンガル問題を心配していたこともあったので、日本語教育も充実していることに魅力を感じ、今の園を選んでいます。
まとめ
2歳~3歳頃から英語を始めさせたいと考えるなら、インターナショナルプリスクールへ入学するのは、有効的な選択肢
学費の高さなど、全くデメリットがないわけではありませんが、私は、2歳の娘をインターナショナルプリスクールに通わせてよかったと思っています。
・日常生活として本物の英語に触れられる
・英語へ苦手意識を払しょくできる
と、プリスクールに通えば、早期の英語学習にとって大事な環境を整えてあげることができるためです。
現在は、「幼児教育無償化」の対象となっているプリスクールも増えているので、通園するのに昔ほどのハードルの高さはないと思います。
2歳~3歳の英語を始めたいお子さんには、インターナショナルプリスクールはおすすめです!


お気軽にコメントをどうぞ